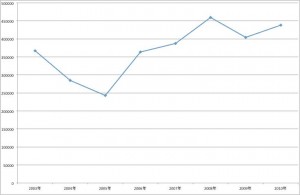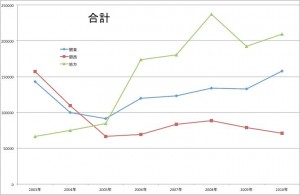~ 反則についてのアンケートから ~
星野繁一(龍谷大学) 髙木應光(NPO神戸居留地研究会)
キーワード:反則、マナー、ロー、ルール、危機感
【目的】
最近ラガーマンの不祥事が目立つ。また試合中にガッツポーズをする者、レフリーに抗議する者などもいる。倫理観の劣化したラガーマンの増加が気にかかる。そこでルールに対するアンケートを実施し、倫理観などを分析してみた。
【調査方法】
先行研究は少々古いが、木幡日出男(現成徳大学教授)「ファウルついての考え方~中学生サッカー選手の調査から」(1989年サッカー医・科学研究会)をベースにアンケート票を作成した。関西学生リーグの6大学319、大阪・兵庫の中高生131、スクール・高校指導者70、総計520名からアンケートを回収し集計結果を得た。
【結果と考察】
アンケート結果を5つの分野に分け、大学生を中心に中高生や指導者の結果と対比させながら分析・考察を試みた。
(*①~⑲は質問番号、質問票は別紙)
1)プレーヤーとレフリー
②レフリーの判定について、不服とする学生が実に91.8%もいたが、③判定には一応素直に従っている、という者が79.6%・8割もいた。
2)遵法精神
⑪レフリーに見つからないように、とする学生が44.2%と驚かされる。明らさまに⑬退場やイエローカードにならない限り、と開き直る学生は8.2%と少ない。一方⑥戦術としての反則、に反対する者が63.9%と多い。即ちチームではなく個々が隠れて反則することを是としている。サッカーと比べ反則が見えにくいラグビーでは遵法精神やフェアプレー精神がなければ試合が成立たないとの理解に欠ける学生が多い。
3)スポーツマンシップ
⑭スポーツマンシップを心がけて試合する、には75.9%の学生が賛成としているが、⑮スポーツマンなら反則しないのは当然、には37.9%の賛成しかない。スポーツマンシップとは反則しないのは勿論のこと、相手やレフリーにも敬意を持って試合に臨むことである。
4)反則と勝敗
⑲反則と勝利の間で「B分らない」と迷い悩む回答は中高生で25.2%、だが大学生は42.0%と多い。とは言え⑨勝つためには反則も必要⑲反則してでも勝利を求める、という学生は⑨37.6%⑲36.7%と4割近い。これに反対する中高生⑨67.2%⑲61.1%指導者⑨88.6%⑲81.4%とは非常に大きな差がある。いかに大学生たちの間に勝利至上主義が蔓延しているかが分る。“Good looser”は死語となったのだろうか。
5)ラグビーの目的
⑰一番大切なことは勝利ではない、に反対する学生が49.5%に対し指導者は52.9%と全く逆な回答が示されている。大学生は勝利を最終目的にしていて、目的と手段(目標=勝利)が本末転倒の状況にある。あくまでも結果を求められるプロと同様、勝利至上主義に陥っているといえる。
【まとめ】
倫理観を問うた⑥~⑲の中で大学生が「B分らない」と答えた項目が非常に多い。Bが最多数(40~47.3%)を占めたのが⑥⑮⑯⑱⑲の5項目、同様Bが30%以上の項目が6つ,計11項目もあった。即ちルールに対して迷い悩み葛藤し、倫理観が劣化している学生が多数存在する。ここに指導の余地があるのではないか。温故知新、ラグビーは英国パブリックスクールに於いてジェントルマンを育てるためのスポーツとして行われてきた。悩み多き迷える学生ラガーマンを救えるのは、ラグビー界の大人でしかない。現状のままでは、更なる勝利至上主義・商業主義・拝金主義、そして筋肉増強剤・薬物使用が、はびこるのは時間の問題であり不祥事も益々増えるであろう。